バレンタイン前夜のこぼれ話
2ページ目がお気に入り
---
第八神機エノアは、山と積まれた器具の前に困惑していた。
大量の鍋と、大量のプラスチック容器。耐熱性のヘラに、包丁。ホイップ絞り器。机の上を所狭しと占拠したそれら。
目的は、チョコレート作り。だがその過程に山積みとなった器具たちに、エノアは率直に言えばフリーズしていた。
人間的に言うならば、あっけを取られていた、とか。呆然としていた、とかだろうか。アホ毛はぐるり、ぐるりと困惑を示すように回り、青色の瞳はくるり、くるりと回っていた。
「………なあ、手伝おうか?」
声をかけるのは、ミコト。かくいう彼女に、菓子作り等という高尚な行いの経験はない。けれども、少なくともどういう風に作業をすればよいのか、なんてことは理解できるだけの柔軟さがあった。
なにせ彼女の妹は、おしゃれ大好きでスイーツ好きの今時を駆け抜けるような人だから、どういう風に料理するのだとか、どういう風に機材を使うのだとかは、それなりに理解があった。
というか、そんな知識とか経験があるとか、そういうのは関係なく。ここで彼女に声をかけないのは、流石に酷だった。
ミコトも、アミも、ここにはいないレーベンも。気色悪いレベルで妹の危機を察知できるゾーエーも、見解は一致している。多分、この状況であってなんら関係性のないジャンでさえ、その気苦労性の性格から、手伝おうと言い出したはずだ。
それくらいに今のエノアは哀れだった。なんていうか、もういろいろと。菓子作りでやっちゃいけないことを全部やってるのが、もう本当に哀れだった。
けれども、第八神機エノアには、確かな意地と、揺るぎない信念があった。
なにせ最近は手作りにはまっているエノア。人間たりうることは手作りにありと、工業技術の結晶が、工業技術のない時代を羨むような皮肉を覚えてしまったのがすべての元凶。とはいえある意味で正しい理論的な動き。それが暴走するとどうなるかといえば、これだ。
チョコ作りの最初の一ページには、だいたいこんなことが書いてある。
「道具はしっかり準備して、レシピは読み込んで、レシピ通りに作れよ。最初に作業工程見てわかんないところあったら事前に調べといてよ。菓子作りは時間勝負」
では、道具を「しっかり」準備するの、機械的な定義は?
「少ないよりも多いほうがマシ」である。
残念ながら、作業スペースを十分に確保しろ、という文章は2ぺージ目に書いてあった。インタプリタ言語が大嫌いなエノアの癖に、思考順序は完全にインタプリタだった。
「………一人で頑張ってみる」
呆然としながらつぶやかれた言葉に、ミコトは天を見上げ、それでも何とか持ち直した彼女は、
「まあ、頑張れ。応援してる」
の一言とともに、椅子へ座りなおしたのだった。
それから早5時間の出来事である。
レシピブックを読み込んで1時間。わからないところだらけだったエノアが各レシピをシーケンスで練習しだしてから3時間。意気 揚々と作成し始め、うまくいかないことに不満げになってから5時間。
ブツブツ、ブツブツとつぶやくのは、料理作りが初めてならだれでも思う「アレ」だった。
「塩をしょうしょう」とか。「ぐつぐつになるまで煮込む」とか。「泡立ってきたら」とか。
まあ、それこそ「あんじょうしといてください」なのだが。実際、これを定量的に定義するのは難しいと、誰もが思う。けれどもそういった道理を放っておいて、「それってどの状態なんだよ」と言いたくなるのは、自然の道理なのだ。
そしてそれにマトモな回答を当てるのであれば、「母親とかに料理の仕方習わんかった?」であり、そして残酷なことに、機械の彼女に母親という概念はない。強いて当てはめるとしても、彼女の開発者は2千年位前に首を吊っているので、習う余地もない。なんなら、仮に生きていたとしても彼女自身も料理ができない。人によって差はあれど、科学者なんてだいたいそんなものである。
「…これでチョコレートがすべて滑らかに…滑らかにってこれでいいの………? 感覚的過ぎ。定量的に、今の攪拌率は___」
実に哀れだった。
それを肴にするのはアミ。ひとえにこれが頑張っているエノアを馬鹿にするの姿勢であれば恐ろしいほどの暴挙だったが、これが「愛するレーベンのために頑張って必死に一人で全部やろうとして、なんなら渡すときの包装も頑張るのだろうしそれを想像したら…ご飯5杯はいけますわね」だとか考えているものだから、どのみちヤベーやつである。
「チョコづくりねぇ。アミはやったことあるっけ?」
彼女を妄想の世界から引き戻したのはミコト。アミは咳ばらいをしながら、唇の端の涎を拭いた。
「まあ、あるといえばありますわよ。まあ、結局リンがすべてやってしまったというか。わたくしは一切手を触れてませんけど」
思い出すのは、まだ足が動いていたころ。まだマトモだった家族の輪の中で、姉妹一緒に作るチョコレート。ただし、姉ラブなリンはこの当時「姉のチョコを食べる」といった欲望はなく、「姉に手作りチョコを食べさせてあげたい」なんて方向の愛しかなかったものだから、すべて自分でやってしまったのだ。
悲しいことに、「姉手作りの愛情たっぷりチョコ食いてぇ」の欲望が芽生えるころには、リンとアミは別居していたし、アミは車いす生活で、料理にも無気力だった。世の中は残酷である。
「まあ、私にとって一番縁遠いのが料理ですもの。これまでも、これからも、他人が作ったものを食べるほうが楽しいですわ」
楽ですしね、と口添えしたアミに、ミコトはうなづく。
「………ところで、なんだけど。その妹さんがやってたときもさ、あんな感じだったわけ?」
ミコトは苦々しげにつぶやく。
山と積まれた容器の山。くしゃくしゃとまとめられたビニール袋にサランラップ。まな板の上には刻まれたチョコの破片。邪魔でどけたホイップ絞り器は、汚れたボウルの中に突き刺さっている。
アミは、流石に今度ばかりは苦々しげな顔をして、唇をゆがませた。
「………まあ、凝ったものを作ってるみたいですし………」
甘いものはそこまで食べないレーベンのために、甘さ控えめのビターチョコ。…を、ケーキのようにする。
ケ ー キ の よ う に す る。
なぜ料理初心者は、自分の手の届かない領域に手を出すのだろう。答えは、「憧れは止められねぇんだ」である。
「ま、まあ。意外に不器用なところも、エノアらしいですもの」
「そうかな? そうかも………。いや、そうだな」
そういうことにしておくのが一番カッコいいのである。それを小耳にはさんでいるエノアは、ぶすっとした顔をしていたが。
はてさて、エノアはしっかりとレーベンに贈り物をできるのか。そして、レーベンはしっかりとエノアへ贈り物をできるのか?
すべては二人が目標を低く設定しなおせるかに割とマジで切実に懸かっている!
次回、「ドイツのバレンタインは男性が恋人に贈り物をする。………待てよ、百合の場合は………?」
こうご期待!!
---
第八神機エノアは、山と積まれた器具の前に困惑していた。
大量の鍋と、大量のプラスチック容器。耐熱性のヘラに、包丁。ホイップ絞り器。机の上を所狭しと占拠したそれら。
目的は、チョコレート作り。だがその過程に山積みとなった器具たちに、エノアは率直に言えばフリーズしていた。
人間的に言うならば、あっけを取られていた、とか。呆然としていた、とかだろうか。アホ毛はぐるり、ぐるりと困惑を示すように回り、青色の瞳はくるり、くるりと回っていた。
「………なあ、手伝おうか?」
声をかけるのは、ミコト。かくいう彼女に、菓子作り等という高尚な行いの経験はない。けれども、少なくともどういう風に作業をすればよいのか、なんてことは理解できるだけの柔軟さがあった。
なにせ彼女の妹は、おしゃれ大好きでスイーツ好きの今時を駆け抜けるような人だから、どういう風に料理するのだとか、どういう風に機材を使うのだとかは、それなりに理解があった。
というか、そんな知識とか経験があるとか、そういうのは関係なく。ここで彼女に声をかけないのは、流石に酷だった。
ミコトも、アミも、ここにはいないレーベンも。気色悪いレベルで妹の危機を察知できるゾーエーも、見解は一致している。多分、この状況であってなんら関係性のないジャンでさえ、その気苦労性の性格から、手伝おうと言い出したはずだ。
それくらいに今のエノアは哀れだった。なんていうか、もういろいろと。菓子作りでやっちゃいけないことを全部やってるのが、もう本当に哀れだった。
けれども、第八神機エノアには、確かな意地と、揺るぎない信念があった。
なにせ最近は手作りにはまっているエノア。人間たりうることは手作りにありと、工業技術の結晶が、工業技術のない時代を羨むような皮肉を覚えてしまったのがすべての元凶。とはいえある意味で正しい理論的な動き。それが暴走するとどうなるかといえば、これだ。
チョコ作りの最初の一ページには、だいたいこんなことが書いてある。
「道具はしっかり準備して、レシピは読み込んで、レシピ通りに作れよ。最初に作業工程見てわかんないところあったら事前に調べといてよ。菓子作りは時間勝負」
では、道具を「しっかり」準備するの、機械的な定義は?
「少ないよりも多いほうがマシ」である。
残念ながら、作業スペースを十分に確保しろ、という文章は2ぺージ目に書いてあった。インタプリタ言語が大嫌いなエノアの癖に、思考順序は完全にインタプリタだった。
「………一人で頑張ってみる」
呆然としながらつぶやかれた言葉に、ミコトは天を見上げ、それでも何とか持ち直した彼女は、
「まあ、頑張れ。応援してる」
の一言とともに、椅子へ座りなおしたのだった。
それから早5時間の出来事である。
レシピブックを読み込んで1時間。わからないところだらけだったエノアが各レシピをシーケンスで練習しだしてから3時間。意気 揚々と作成し始め、うまくいかないことに不満げになってから5時間。
ブツブツ、ブツブツとつぶやくのは、料理作りが初めてならだれでも思う「アレ」だった。
「塩をしょうしょう」とか。「ぐつぐつになるまで煮込む」とか。「泡立ってきたら」とか。
まあ、それこそ「あんじょうしといてください」なのだが。実際、これを定量的に定義するのは難しいと、誰もが思う。けれどもそういった道理を放っておいて、「それってどの状態なんだよ」と言いたくなるのは、自然の道理なのだ。
そしてそれにマトモな回答を当てるのであれば、「母親とかに料理の仕方習わんかった?」であり、そして残酷なことに、機械の彼女に母親という概念はない。強いて当てはめるとしても、彼女の開発者は2千年位前に首を吊っているので、習う余地もない。なんなら、仮に生きていたとしても彼女自身も料理ができない。人によって差はあれど、科学者なんてだいたいそんなものである。
「…これでチョコレートがすべて滑らかに…滑らかにってこれでいいの………? 感覚的過ぎ。定量的に、今の攪拌率は___」
実に哀れだった。
それを肴にするのはアミ。ひとえにこれが頑張っているエノアを馬鹿にするの姿勢であれば恐ろしいほどの暴挙だったが、これが「愛するレーベンのために頑張って必死に一人で全部やろうとして、なんなら渡すときの包装も頑張るのだろうしそれを想像したら…ご飯5杯はいけますわね」だとか考えているものだから、どのみちヤベーやつである。
「チョコづくりねぇ。アミはやったことあるっけ?」
彼女を妄想の世界から引き戻したのはミコト。アミは咳ばらいをしながら、唇の端の涎を拭いた。
「まあ、あるといえばありますわよ。まあ、結局リンがすべてやってしまったというか。わたくしは一切手を触れてませんけど」
思い出すのは、まだ足が動いていたころ。まだマトモだった家族の輪の中で、姉妹一緒に作るチョコレート。ただし、姉ラブなリンはこの当時「姉のチョコを食べる」といった欲望はなく、「姉に手作りチョコを食べさせてあげたい」なんて方向の愛しかなかったものだから、すべて自分でやってしまったのだ。
悲しいことに、「姉手作りの愛情たっぷりチョコ食いてぇ」の欲望が芽生えるころには、リンとアミは別居していたし、アミは車いす生活で、料理にも無気力だった。世の中は残酷である。
「まあ、私にとって一番縁遠いのが料理ですもの。これまでも、これからも、他人が作ったものを食べるほうが楽しいですわ」
楽ですしね、と口添えしたアミに、ミコトはうなづく。
「………ところで、なんだけど。その妹さんがやってたときもさ、あんな感じだったわけ?」
ミコトは苦々しげにつぶやく。
山と積まれた容器の山。くしゃくしゃとまとめられたビニール袋にサランラップ。まな板の上には刻まれたチョコの破片。邪魔でどけたホイップ絞り器は、汚れたボウルの中に突き刺さっている。
アミは、流石に今度ばかりは苦々しげな顔をして、唇をゆがませた。
「………まあ、凝ったものを作ってるみたいですし………」
甘いものはそこまで食べないレーベンのために、甘さ控えめのビターチョコ。…を、ケーキのようにする。
ケ ー キ の よ う に す る。
なぜ料理初心者は、自分の手の届かない領域に手を出すのだろう。答えは、「憧れは止められねぇんだ」である。
「ま、まあ。意外に不器用なところも、エノアらしいですもの」
「そうかな? そうかも………。いや、そうだな」
そういうことにしておくのが一番カッコいいのである。それを小耳にはさんでいるエノアは、ぶすっとした顔をしていたが。
はてさて、エノアはしっかりとレーベンに贈り物をできるのか。そして、レーベンはしっかりとエノアへ贈り物をできるのか?
すべては二人が目標を低く設定しなおせるかに割とマジで切実に懸かっている!
次回、「ドイツのバレンタインは男性が恋人に贈り物をする。………待てよ、百合の場合は………?」
こうご期待!!
11
22
468
2025-02-11 17:46








![illustration, CRYMACHINA, ENOA / [08]-ENOA-](/proxy/i.pximg.net/c/360x360_70/img-master/img/2024/09/16/15/58/12/122487581_p0_square1200.jpg)

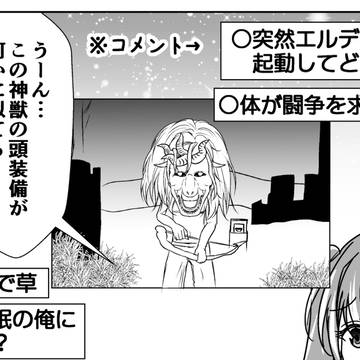



































































































Comments (2)
ジャンに教えてもらうレーベン、新旧主人公のバトンタッチを抽象的に描いているようで尊い……
View Replies